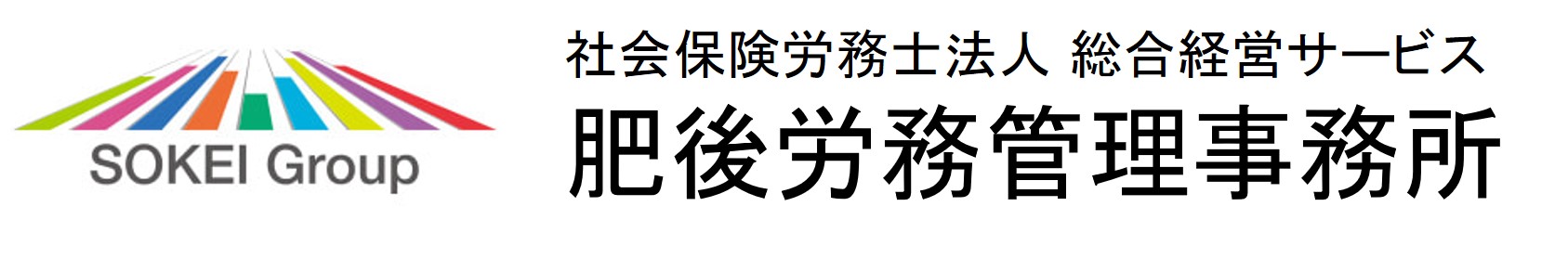【2025年版】保険料控除申告書の書き方(生命保険・地震保険・社保・iDeCo)
2025/12/06
この記事は「従業員が自分の申告書を書くため」のマニュアルです。
しかし、「提出された大量の控除証明書(ハガキ)と申告書を1枚ずつ突き合わせてチェックする」のは、貴方の仕事です。
保険料控除は「添付漏れ」や「計算ミス」が最も多く、チェック業務の負担が最大です。
> 「紙の回収・チェック地獄」から脱却したい方へ。来期に向けたご相談はこちら
最終更新日: 2025-12-06
年末調整の「保険料控除申告書」の書き方を、控除証明書の見方から「年間総額」の記入、生命保険3区分、iDeCo申告まで、実務フローで整理。提出前チェックリスト・FAQ付き。
お急ぎの方へ:
まずは下の「この記事のポイント」と「提出前チェックリスト」だけでOK。
5分で「保険料控除申告書」の重要箇所(生命保険3区分・iDeCo・証明書添付・年間総額)を確認できます。
本記事は、年末調整シリーズの最終回として、「給与所得者の保険料控除申告書」(以下、保険料控除申告書)の書き方を、実務目線で迷わず進められるよう整理しました。
控除証明書の添付ルール、生命保険料の3区分、「年間総額」の記載、iDeCoの申告などを中心に、提出前に便利な早見表・チェックリスト・FAQ付きで解説します。
監修: 社会保険労務士法人 総合経営サービス(東京都北区)
この記事のポイント(提出前チェックで5分確認)
- 控除証明書の添付が原則:保険会社等から届く「控除証明書」の原本(または電子データ)の添付が必要です。
- 生命保険は3区分:「一般の生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」の3区分を正しく分けて記入します。
- 金額は「年間総額」で記入:証明書発行時点の既払額ではなく、12月31日までの支払予定額(年間総額)を記載します。
- 社会保険料控除:年の途中で転職して国民健康保険料を払った場合、その金額を申告できます(証明書添付は不要)。
- iDeCo・小規模企業共済:全額が所得控除の対象です。掛金の「控除証明書」に基づき、忘れず申告しましょう。
- 申告ゼロでも提出:該当する控除がない場合でも、「申告漏れではない」ことを示すため、空欄のまま提出するのが実務上スムーズです。
※ 会社配布の様式により各欄の上下位置が異なる場合があります。実物の様式を優先してください。
目次
- 「保険料控除申告書」とは?提出する目的
- 判断の大原則(証明書の添付・年間総額・契約者名)
- 書き方の流れ(4ブロック別:生保・地震・社保・小規模)
- 控除の種類・早見メモ(実務者向け)
- 控除証明書を見ながら最終チェック(よくある間違い)
- ケース別シミュレーション(代表例)
- 動画で実践(第3回)|記事と動画の使い分け
- よくある質問(FAQ)
1. 「保険料控除申告書」とは?提出する目的
「保険料控除申告書」は、あなたがその年に支払った各種保険料や掛金を会社へ申告し、税金の元となる所得から差し引く「所得控除」を受けるための書類です。
マル扶(第1回)や基配所(第2回)が「人の状況」を申告するのに対し、この書類は「支払ったお金」を申告するのが特徴です。税額に直結するため、非常に重要な書類です。
2. 判断の大原則(証明書の添付・年間総額・契約者名)
- ① 控除証明書の添付:申告の根拠として、保険会社等から発行される「控除証明書」の原本(またはデータ)の添付が必須です(国民健康保険料を除く)。
- ② 12月までの年間総額で記入:証明書に「ご申告額」や「12月までの支払予定額」として記載されている年間総額を転記します。10月時点の既払額ではありません。
- ③ 契約者名義:契約者が本人でなくても、申告者本人(世帯主など)が保険料を支払っている場合は控除の対象となります(例:妻名義の保険料を夫が支払っている)。
3. 書き方の流れ(4ブロック別:生保・地震・社保・小規模)
申告書は上から下に、大きく4つのブロックに分かれています。図解(図1)と照らし合わせながらご確認ください。
3-1. ① 生命保険料控除
申告書の最上部、最も大きな欄です。控除証明書を見ながら、3つの区分に正しく分類します。
- 一般の生命保険料(新・旧):死亡保険や学資保険など。
- 介護医療保険料:医療保険やがん保険など。
- 個人年金保険料(新・旧):税制適格特約が付いた個人年金。
証明書に「一般用」「介護医療用」などと記載されているので、その通りに転記します。平成24年(2012年)1月1日を境に「新制度」「旧制度」に分かれており、控除額の計算方法が異なるため注意が必要です。それぞれ記入後、申告書内の計算式に当てはめて控除額を算出します。
3-2. ② 地震保険料控除
中段の欄です。控除証明書に基づき記入します。
- 地震保険料:地震保険の部分。
- 旧長期損害保険料:平成18年(2006年)12月31日までに契約した、満期返戻金のある10年以上の損害保険(火災保険など)。
区分を間違えずに記入し、控除額を計算します。
3-3. ③ 社会保険料控除
中段の欄です。給与から天引きされている社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)は記入不要です。それ以外で支払ったものが対象です。
- 国民年金保険料:日本年金機構から届く「控除証明書」の添付が必要です。
- 国民健康保険料:年の途中で転職した方などが支払った場合。控除証明書の添付は不要ですが、支払った市区町村と年間の支払総額を記入します。
この控除は、支払った金額が全額所得控除になります。
3-4. ④ 小規模企業共済等掛金控除
最下部の欄です。将来の積立で、節税効果が非常に高い項目です。
- iDeCo(個人型確定拠出年金):国民年金基金連合会から届く「控除証明書」が必要です。
- 小規模企業共済:(独)中小企業基盤整備機構から届く証明書が必要です。
この控除も、支払った掛金の全額が所得控除になります。
4. 控除の種類・早見メモ(実務者向け)
| ブロック | 主な対象 | 証明書 | 実務の勘所 |
|---|---|---|---|
| ① 生命保険料 | 死亡保険・医療保険・個人年金 | 必須 | 「一般」「介護医療」「個人年金」の3区分を厳守。新/旧の区分も注意。 |
| ② 地震保険料 | 地震保険・旧長期損害保険 | 必須 | 証明書に「地震」「旧長期」どちらで記載されているかを確認。 |
| ③ 社会保険料 | 国民年金・国民健康保険 | 国民年金は必須 国民健康保険は不要 |
給与天引き分は書かない。国保は添付不要だが、支払総額の把握が必要。 |
| ④ 小規模共済等 | iDeCo・小規模企業共済 | 必須 | 全額が所得控除となる最重要項目の一つ。証明書の添付漏れに注意。 |
5. 控除証明書を見ながら最終チェック(よくある間違い)
この申告書の間違いは「計算」よりも「分類」で起こります。手元に届いた控除証明書のハガキを見ながら、最終チェックをしましょう。
- (誤)医療保険やがん保険の証明書を、「一般」の欄に書いてしまった。
- (正)証明書をよく見てください。「介護医療用」と記載があるはずです。これは「① 生命保険料控除」ブロックの中の「介護医療保険料」の欄(真ん中)に書くのが正解です。
- (誤)iDeCoの証明書を、「個人年金」の欄に書いてしまった。
- (正)iDeCo(個人型確定拠出年金)は、「① 生命保険料控除」ではなく、申告書の一番下にある「④ 小規模企業共済等掛金控除」の欄に書きます。控除額が全く異なるため、最も注意すべき分類ミスです。
- (誤)証明書に「支払額 80,000円」「ご申告額 100,000円」とあり、8万円を書いた。
- (正)「支払額」は10月時点などの既払額です。年末調整では「12月までの支払予定額」である「ご申告額(この例では10万円)」を使います。
- (誤)国民健康保険料の証明書がないので、申告をあきらめた。
- (正)国民健康保険料の控除申告に、証明書の添付は不要です。市区町村の納付記録や通帳などでご自身が支払った年間の総額を確認し、「③ 社会保険料控除」の欄に記入すれば、全額が控除対象となります。
🚨 担当者が泣かされる「再計算の罠」
保険料控除は、従業員が「新・旧」の区分を間違えたり、計算式を誤ることが非常に多い項目です。
もし12月の給与計算後にミスが発覚すると、「源泉徴収票の再発行」や「給与の過不足精算」という重い手戻りが発生します。
6. ケース別シミュレーション(代表例)
| ケース | 前提 | 見る欄 | 実務の勘所 |
|---|---|---|---|
| iDeCoに加入 | 毎月2万円(年間24万円)を拠出 | ④ 小規模企業共済等 | 「控除証明書」に記載の年間総額(24万円)を記入。24万円全額が所得控除対象。 |
| 生保・医療・地震に加入 | 一般生命保険(年8万)、医療保険(年6万)、地震保険(年2万) | ① 生命保険料 ② 地震保険料 |
生保(一般)と医療保険(介護医療)を区分して記入。それぞれ控除額を計算。地震保険も記入。 |
| 転職して国保を払った | 10月入社。8〜9月分の国保料10万円を自分で納付。 | ③ 社会保険料控除 | 「国民健康保険」として10万円を記入。証明書添付は不要。支払った10万円全額が所得控除対象。 |
注:ここでの金額・区分は考え方を示すサンプルです。実際の控除額は「控除証明書」と申告書の「記載要領」で必ずご確認ください。
7. 動画で実践(第3回)|記事と動画の使い分け
この記事を読んだことで、あなたが「何を」「なぜ」申告書に書くべきかの理論(=WHAT/WHY)は完璧です。
次のステップは、「どう書くか」の実践(=HOW)です。
下の動画では、専門家が実際の申告書(様式)と控除証明書(実物サンプル)を並べ、どの数字を・どの欄に転記するのか、その「手の動き」を最初から最後まで解説します。
この記事で理論を学んだ後に見ることで、理解度が100%定着します。
年末調整シリーズはこちら:
第1回|扶養控除等申告書(マル扶)の書き方
第2回|基礎控除・配偶者控除等申告書(基配所)の書き方
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 控除証明書を紛失しました。どうすればいいですか?
A. すぐに契約している保険会社やiDeCoの運営機関に連絡し、再発行を依頼してください。証明書(原本またはデータ)の添付がないと、原則として控除は受けられません。
Q2. 契約者が妻(または子)名義の生命保険料も控除できますか?
A. 契約者が誰かに関わらず、申告者本人(あなた)がその保険料を実際に支払っているのであれば、あなたの控除として申告可能です。
Q3. 申告する保険が何もありません。提出は不要ですか?
A. 提出を推奨します。会社(給与担当者)が「申告漏れ」なのか「対象なし」なのかを判断できません。空欄(ブランク)のまま提出することで、「申告するものがない」という意思表示になり、実務上スムーズです。
Q4. 国民健康保険料の証明書は添付しなくていいのですか?
A. はい。国民健康保険料については、控除証明書の添付は法令上求められていません。納付書や口座履歴などでご自身が支払った年間の総額を確認し、申告書に記入してください。
社会保険労務士法人 総合経営サービス 肥後労務管理事務所:https://sokei-sr.jp/
【王子オフィス】
〒114-0002
東京都北区王子2-12-10 総経ビル
【吉祥寺オフィス】
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-14 メディ・コープビル8 501号室
【信州松本オフィス】
〒390-0833
長野県松本市双葉 11-12