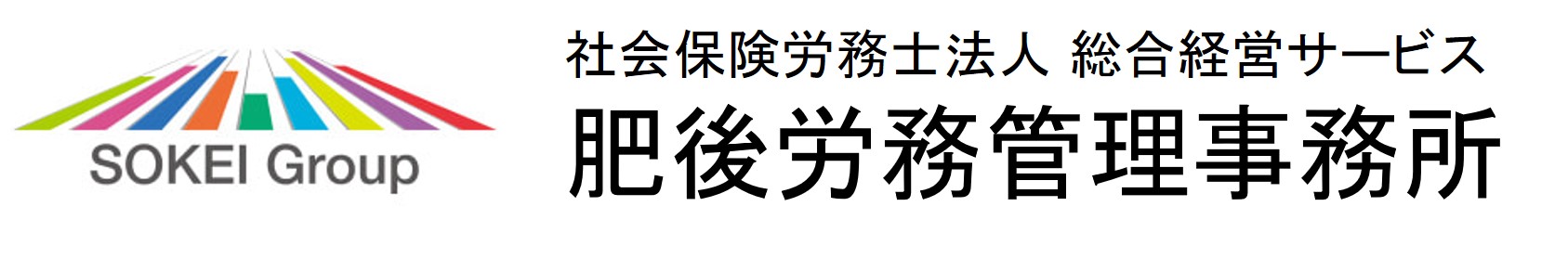【2025年版】基礎控除・配偶者控除・特定親族特別控除・所得金額調整控除の書き方
2025/12/06
この記事は「従業員が自分の申告書を書くため」のマニュアルです。
もし貴方が「従業員が書いた申告書をチェックして計算する立場」であれば、
この記事だけでは不十分です。
今年は「定額減税」の影響で、チェック漏れが「会社側の未払いリスク」に直結します。
> 来年こそは楽になりたい方へ。「業務フロー見直し」のご相談はこちら
最終更新日: 2025-12-06
お急ぎの方へ:
まずは下の「この記事のポイント」と「提出前チェックリスト」だけでOK。
5分で「基礎控除・配偶者控除・特定親族特別控除・所得金額調整控除(=通称“基配書”)」の重要箇所を確認できます。
本記事は、年末調整で提出する「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(以下、基配書)の書き方を、実務目線で迷わず進められるよう整理しました。
判断基準日(12/31)、「収入」と「所得」の違い、年齢・所得による控除額の考え方を中心に、提出前に便利な早見表・チェックリスト・FAQ付きで解説します。
監修: 社会保険労務士法人総合経営サービス 肥後労務管理事務所(東京都北区)
この記事のポイント(要約)
- 12月31日基準で判定:年末時点の事実で判断。途中の増減で判定しない。
- 金額は「所得」で記入:給与は給与所得控除後、年金は公的年金等控除後の金額を用いる。
- 配偶者控除は“世帯主所得×配偶者所得”で決まる:双方の所得帯で控除額が変動。
- 特定親族特別控除:おおむね19歳以上23歳未満で、年収123万円を超える大学生等に関する控除(2025年新設欄)。
- 所得金額調整控除:給与収入850万円超かつ一定要件(特別障害者・23歳未満の扶養等)で申告可能。
目次
- 「基配書」とは?提出する目的
- 判断の大原則(12/31基準・収入/所得・年齢区分)
- 書き方の流れ(4ブロック別:基・配・特・所)
- 控除の考え方・早見メモ(実務者向け)
- 初心者がやりがちな4つの落とし穴
- 記入箇所クイックガイド
- 動画で具体的に確認(第2回)
- ケース別シミュレーション(代表例)
- よくある質問(FAQ)
1. 「基配書」とは?提出する目的
「基配書」は、本人の基礎控除・配偶者控除(特別控除含む)・特定親族特別控除・所得金額調整控除をまとめて会社へ申告する書類です。
年末調整で用いられますが、本来は毎月の源泉所得税の基礎情報としても重要です。
2. 判断の大原則(12/31基準・収入/所得・年齢区分)
- 12/31基準:年末時点の事実で判断(所得・年齢・扶養状況)。
- “収入”ではなく“所得”で記入:給与=給与所得控除後、年金=公的年金等控除後。
- 年齢区分:特定扶養・23歳未満など、年齢は12/31時点で判定。
3. 書き方の流れ(4ブロック別:基・配・特・所)
3-1. 基礎控除(基)
本人の所得に応じて基礎控除額が決まります。
実務のポイントは、該当する所得帯を正しく判定し、控除額を欄に転記すること。判定表が付属している場合は、その表に従います。
3-2. 配偶者控除・配偶者特別控除(配)
- 配偶者の金額は所得(給与所得控除後)で見積。
- 世帯主の所得帯 × 配偶者の所得帯の交差で控除額が決まります(判定表の交点)。
- 控除欄は「配偶者控除」か「配偶者特別控除」かを適用欄で識別して記入。
例:世帯主の所得区分A、配偶者の所得区分「3」に該当 ⇒ 交点の金額を配偶者特別控除欄へ。
3-3. 特定親族特別控除(特)
2025年に新設された申告欄です。
おおむね19歳以上23歳未満で、年収123万円を超える大学生等を念頭にした控除で、給与所得控除後の“所得”帯で控除額が段階的に決まります。
年収が一定額(例:150万円付近など)を超えると控除額が減少し、ある上限(例:188万円付近など)まで緩やかに逓減します。該当者がいる場合は必ずこの欄を使用してください。
3-4. 所得金額調整控除(所)
- 給与収入が850万円超で、かつ次のいずれかに該当:
① 本人・配偶者・扶養親族のいずれかが特別障害者/② 23歳未満の扶養親族がいる など。 - 金額は(給与収入 − 850万円)の10%を目安に計算(上限あり)。
- 複数条件を満たしても、重複加算は不可(1回のみ)。
4. 控除の考え方・早見メモ(実務者向け)
| ブロック | 見るべき指標 | 実務の勘所 |
|---|---|---|
| 基礎控除(基) | 本人の合計所得金額 | 「収入」ではなく“所得”で判定。付属表の該当帯にチェック→額を転記。 |
| 配偶者(配) | 世帯主所得帯 × 配偶者所得帯 | 交点の金額を控除欄へ。配偶者控除/配偶者特別控除の区別を適用欄で必ず確認。 |
| 特定親族(特) | 年齢:19〜22歳/年収123万円超 | 給与所得控除後の所得帯で金額が段階変動。該当者がいればこの欄が必須。 |
| 所得調整(所) | 給与収入850万円超+要件 | 計算式は概ね(収入−850万円)×10%(上限あり)。重複加算なしに注意。 |
5. 初心者がやりがちな4つの落とし穴
- 収入と所得の混同:給与は給与所得控除後、年金は公的年金等控除後の所得で記入。
- 年齢の判定ミス:特定扶養・23歳未満など、12/31時点で区分。
- 新設欄の未申告:年収123万円超の大学生等は特定親族特別控除欄へ。
- 所得金額調整控除の重複:条件が複数あっても1回のみ。上限にも注意。
🚨 担当者が注意すべき「第5の落とし穴」
従業員が正しく記入しても、「会社側の計算チェック」でミスが発生すると、会社がペナルティを受けます。
特に今年は定額減税の処理が加わるため、従来の知識だけで検算を行うのは非常に危険です。ミスが発覚した場合、再計算や修正申告の手間はすべて担当者にのしかかります。
6. 記入箇所クイックガイド
- ①基礎控除:本人の合計所得金額を判定表で帯確認→該当額を転記。
- ②配偶者:「世帯主の所得帯 × 配偶者の所得帯」の交点金額。
適用欄で「配偶者控除」か「配偶者特別控除」かを必ず確認。 - ③特定親族:(大学生など)19〜22歳かつ年収123万円超。
所得帯で段階的に控除額が決まるため、この欄は記入漏れに注意。 - ④所得調整:給与収入850万円超+一定要件で可。
(収入−850万円)×10%(上限あり)。重複加算は不可。
7. 動画で具体的に確認(第2回)
この記事は要点を短時間で把握するためのものです。
実際の記入位置や分岐の見方は、下の動画で書類の実画面と共にご確認ください。
8. ケース別シミュレーション(代表例)
| ケース | 前提 | 見る欄 | 実務の勘所 |
|---|---|---|---|
| 配偶者パート収入あり | 世帯主:所得区分A/配偶者:年収140万円(給与所得控除後の所得で判定) | ② 配偶者特別控除 | 「世帯主所得帯 × 配偶者所得帯」の交点金額を特別控除欄へ。 ※ 年収ではなく“所得”を使う。 |
| 大学生の子が年収123万円を超える | 子:19〜22歳・年収160万円例(給与所得控除後の“所得”で帯判定) | ③ 特定親族特別控除 | 新設欄。所得帯に応じ控除額が段階変動。 ※ 123万円を超えたら本欄の記載が必須。 |
| 年収850万円超+23歳未満の扶養 | 本人:給与収入1000万円/23歳未満の子あり | ④ 所得金額調整控除 | (収入−850万円)×10%を目安。 ※ 条件複数でも申告は1回、上限あり。 |
注:ここでの金額・区分は考え方を示すサンプルです。実際の控除額は会社配布の判定表・記載要領で必ずご確認ください。
第1回の解説はこちら: 【2025年版】扶養控除等(異動)申告書(マル扶)の書き方
9. よくある質問(FAQ)
Q1. 配偶者の金額は年収で書いても良いですか?
A. いいえ。給与所得控除後の「所得」で記入してください。年収(額面)のまま書くと控除額判定を誤ります。
Q2. 大学生の子が年収123万円を少し超えました。どの欄に書きますか?
A. 特定親族特別控除の欄を使用します。所得帯に応じて控除額が段階的に決まります。
Q3. 所得金額調整控除は、特別障害者と23歳未満扶養の両方がいても二重に使えますか?
A. いいえ。申告は1回のみで、重複加算はできません(上限額にも注意)。
Q4. 途中で所得見積もりが変わったらどうすべき?
A. 年末時点の実績で清算されますが、見積更新で源泉税の過不足を抑えられます。会社の指示に従い速やかに修正提出を。
ご連絡をお待ちしています。
社会保険労務士法人 総合経営サービス 肥後労務管理事務所:https://sokei-sr.jp/
【王子オフィス】
〒114-0002
東京都北区王子2-12-10 総経ビル
【吉祥寺オフィス】
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-14 メディ・コープビル8 501号室
【信州松本オフィス】
〒390-0833
長野県松本市双葉 11-12