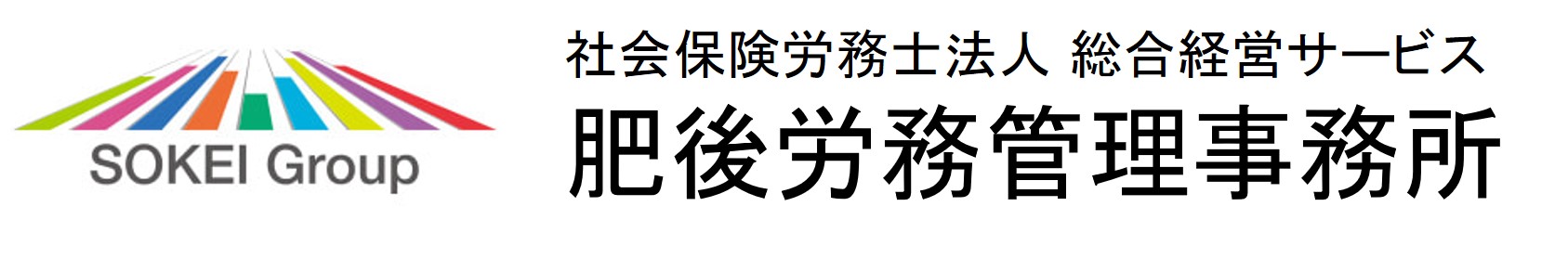【社労士が解説】業務改善助成金が不支給に?「最低賃金割れ」の落とし穴と対策
2025/11/19
こんにちは。社会保険労務士の白井です。日々の業務お疲れ様です。
事業主の皆様にとって、生産性向上と従業員の賃金アップを同時に支援してくれる「業務改善助成金」は、非常に魅力的な制度ですよね。設備投資や研修などに活用し、さらなる事業発展を目指す多くの企業様が利用されています。
しかし、この業務改善助成金、申請すれば誰でも必ずもらえるわけではありません。申請の前提条件として「法令遵守」が求められますが、この点を軽視したために、「まさか」の不支給となってしまうケースがあるのです。
今回は、社労士として多くのご相談を受ける中でも、特に注意喚起したい「最低賃金」に関する不支給事例をご紹介し、助成金を確実に活用するために本当に大切なことについて解説します。
業務改善助成金とは?
まず、業務改善助成金について簡単におさらいしましょう。
これは、中小企業・小規模事業者が生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム導入など)を行い、同時に事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げる場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です(厚生労働省管轄)。
物価高騰が続く中、従業員の生活を守るための賃上げは急務ですが、原資の確保に悩む事業主も少なくありません。この助成金は、そうした「賃上げしたいが、原資が厳しい」という悩みに応え、企業の成長と従業員の待遇改善を後押しする、非常に有用な制度です。
実際にあった不支給事例:「遡って払えば大丈夫」の落とし穴
さて、ここからが本題です。ある事業主様が業務改善助成金の申請を準備していた際、実際に起こった事例です。
事例の概要
その事業所では、助成金の申請準備を進める中で、申請対象となる従業員Aさんの時給が、過去数ヶ月間にわたって地域の最低賃金を下回っていたことが発覚しました。
●地域の最低賃金は、毎年10月頃に改定されることが多いですが、そのチェックが漏れていたのです。
●事業主様は慌てて、最低賃金を下回っていた期間の差額を計算し、Aさんにその不足分全額を「遡及(そきゅう)して」支払いました。
●そして、「これで法令違反の状態は解消された」と考え、遡及支払いを行った証明(疎明書や振込の控えなど)を添付して、労働局に業務改善助成金の交付申請を行いました。
労働局の判断:「不支給」
事業主様は「不足分はすべて支払ったのだから、問題なく受理されるはず」と考えていらっしゃいました。
しかし、後日、労働局から下された判断は、無情にも「不支給」という結果でした。
なぜ、不足分を支払ったにもかかわらず、不支給となってしまったのでしょうか?
労働局の判断理由:
たとえ遡及して不足分を支払ったとしても、助成金の交付申請を行った時点で、過去に「最低賃金法違反」という法令違反をしていた事実は変わらないため。
この判断は、多くの事業主様にとって非常に厳しく感じられるかもしれません。しかし、これは助成金の本質に関わる重要なポイントなのです。
なぜ遡及支払いだけではダメなのか?
助成金審査の基本的な考え方を理解する必要があります。
助成金は、国(厚生労働省)の貴重な財源(主に雇用保険料)を使って、「法律をきちんと守り、その上(プラスアルファ)で、さらに雇用環境を良くしようと努力する事業主」を支援するために支給されるものです。
今回の事例のように、申請時点で「最低賃金法」という労働基準関連法規の根幹とも言える法律を守れていなかった(=法令違反が常態化していた)場合、労働局はどのように判断するでしょうか。
「発覚したから慌てて払った」という行為は、残念ながら「日頃から適正な労務管理ができていなかった証拠」と捉えられてしまう可能性が高いのです。
遡及支払いはもちろん労働者に対して行うべき最低限の義務ですが、それをもって「法令遵守の意識が高い企業」として助成金の支援対象に値する、とは判断されなかったのです。
業務改善助成金で不交付にならないために本当に大切なこと
この苦い事例から、私たちが学ぶべき教訓は非常に明確です。
それは、「助成金申請を思い立ってから慌てて整備する」のではなく、「日頃からの適正な労務管理と法令遵守」こそが、助成金活用の絶対的な前提条件であるということです。
具体的には、以下の3点を徹底することが不可欠です。
1. 正確な最低賃金の把握(毎年更新!)
「うちは時給制じゃないから大丈夫」と思っていませんか? 月給制や日給制であっても、所定労働時間で割った金額が最低賃金を下回っていれば法令違反です。
■ 地域別最低賃金:毎年10月頃に改定されます。必ず最新の金額(厚生労働省や都道府県労働局のHPで確認)を把握してください。
■ 特定(産業別)最低賃金:特定の産業に従事する労働者には、地域別最低賃金より高い金額が設定されている場合があります。自社の業種が該当しないか確認が必要です。
この確認を怠ることが、意図せぬ法令違反の第一歩となります。
2. 日常的な労務管理の徹底(毎月のチェック)
給与計算は「一度設定したら終わり」ではありません。
◆ 毎月の給与計算時に、従業員一人ひとりの時給換算額が最低賃金をクリアしているか確認する習慣をつけましょう。
◆ 労働時間(残業時間含む)の管理は適正ですか? 出勤簿やタイムカードは正確に記録・保管されていますか?
◆ 賃金台帳、労働者名簿、雇用契約書など、法定三帳簿や必要書類は正しく整備されていますか?
これらの「当たり前」を日々適正に運用することが、最強の防衛策となります。
3. 申請前のセルフチェックと「専門家への早期相談」
もし助成金申請を検討し始めたら、「これくらい大丈夫だろう」という自己判断は禁物です。
- 申請書類を作成する前に、まずは自社の労務管理状況(特に賃金台帳や出勤簿)に上記のような問題がないか、厳しくセルフチェックしてください。
- もし少しでも不安な点や、過去の運用に曖昧な部分(例:みなし残業代の計算が正しいか、など)が見つかった場合は、必ず申請手続きに入る前に、私たち社会保険労務士(社労士)にご相談ください。
問題が発覚した場合、助成金申請を一旦見合わせ、先に適正な労務管理体制を構築し、法令遵守の状態を一定期間(例えば半年~1年)維持することが先決となる場合もあります。
まとめ:法令遵守は助成金活用の「スタートライン」
業務改善助成金は、正しく活用すれば、企業の生産性と従業員の満足度を同時に高められる素晴らしい制度です。
しかし、その活用は「法令遵守」という強固な土台の上にはじめて成り立ちます。今回の事例のように、「最低賃金割れ」という基本的な法令違反があると、せっかくの設備投資や賃上げの意欲も、助成金という形での支援には結びつきません。
助成金をもらうために法令を守るのではなく、従業員が安心して働ける環境を整備するために法令を守る。その結果として、助成金も活用できる――。
この順番を間違えてはいけません。
今回のコラムが、皆様の会社の労務管理体制を今一度見直すきっかけとなれば幸いです。適正な労務管理や助成金申請についてお困りのことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。
著者情報
執筆者:社会保険労務士法人総合経営サービス肥後労務管理事務所
社会保険労務士 代表社員 白井 章稔
社会保険労務士法人 総合経営サービス 肥後労務管理事務所:https://sokei-sr.jp/
【王子オフィス】
〒114-0002
東京都北区王子2-12-10 総経ビル
【吉祥寺オフィス】
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-14 メディ・コープビル8 501号室
【信州松本オフィス】
〒390-0833
長野県松本市双葉 11-12