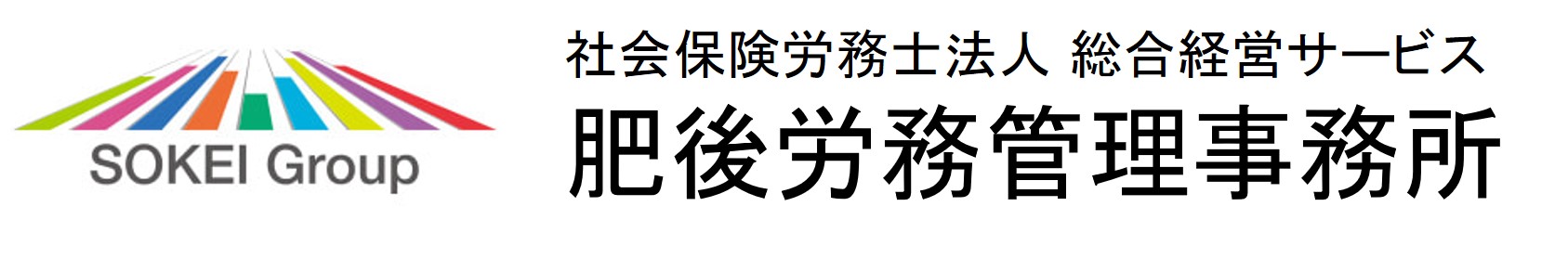業務改善助成金の交付決定はまだ!? 審査の裏側と「ローカルルール」とは?
こんにちは。社会保険労務士法人総合経営サービス肥後労務管理事務所の白井です。
日々の業務、本当にお疲れ様です。私たち社労士のもとにも、最近多くの経営者様から「業務改善助成金を申請してもらったけど、交付決定はまだですか…」という切実なご相談が寄せられています。
特に2025年度(令和7年度)は、その傾向が顕著です。弊所でも、神奈川県で7月アタマに申請したものが、10月末にようやく交付決定された(それでも約4ヶ月)というケースがありました。一方で、東京、埼玉、千葉では、同時期に申請したものでも、11月を過ぎてもまだ交付決定の連絡がない…といった状況です。
申請をされた経営者様にとっては、設備投資のスケジュールや資金繰りにも関わるため、「一体いつ決まるんだ」「審査はちゃんと進んでいるのか」と、ご不安なことと思います。
この記事では、なぜ今、業務改善助成金の交付決定が遅れているのか、その背景と審査の実態、そしてよく噂される「労働局ごとのローカルルール」について、社労士の視点から分かりやすく解説します。
なぜ? 交付決定が大幅に遅れている最大の理由
まず結論から申し上げますと、遅延の最大の理由は「申請件数の爆発的な増加」にあります。
業務改善助成金は、中小企業の生産性向上と、そこで働く従業員の賃金引上げを支援するとても優れた助成金です。特にここ数年、以下のような要因が重なり、申請が労働局に殺到している状況です。
■ 過去最大級の最低賃金引上げ: 毎年秋に改定される地域別最低賃金が、全国的に大幅に引き上げられています。これに伴い、賃金引上げの原資確保と生産性向上の両立を目指す企業が、この助成金に注目しました。
■ 助成金自体の魅力向上: 助成上限額の引き上げや、特例的なコースの設置、助成率の改善など、制度が拡充され、より使いやすくなったことも申請を後押ししています。
■ 認知度の向上: メディアや我々専門家からの情報発信により、「使える助成金」としての認知度が格段に上がりました。
労働局も「審査遅延」を公式に認める事態に
通常、助成金の審査期間は「申請から1〜2ヶ月程度」が目安とされてきました。しかし、現状はそれを大幅に超えています。
実際、とある労働局のホームページでは、「通常3か月いただいているところ、申請から交付決定までに4~6か月いただいております。」「審査遅延につき大変ご迷惑をおかけしております。」と、公式に審査の遅れを発表・謝罪しているケースもあります。(※熊本労働局の例)
これは、申請件数に対して、審査を行う労働局の担当者(マンパワー)が追いついていないことを如実に示しています。皆様の申請が放置されているわけではなく、順番に処理はされているものの、審査の「順番待ち」が非常に長くなっている、というのが実態です。
交付審査はどのように行われている?
では、労働局ではどのような審査が行われているのでしょうか。不安を解消するためにも、基本的な流れを知っておきましょう。
交付審査は、大きく分けて2つのステップで行われます。
1.形式審査(書類チェック):
まず、提出された申請書類一式(申請書、事業計画書、見積書など)に、漏れや記載ミスがないか、必要な添付書類がすべて揃っているかがチェックされます。ここで不備があると、差し戻しとなり、さらに時間がかかってしまいます。
2.実質審査(内容の確認):
書類が揃っていることが確認されると、次に計画内容の審査に入ります。審査官は主に以下の点を見ています。
●助成金の趣旨との合致: 計画されている設備投資(例:新しいレジ、自動洗浄機など)が、本当に「生産性向上」に繋がり、その結果として「賃金引上げ」が可能になるのか。
●計画の妥当性: 導入する機器が事業内容に対して適切か、金額は妥当か。
●賃金引上げの確認: 「事業場内最低賃金」を「いくら引き上げる」という計画が明確か。
この実質審査で、計画内容に不明瞭な点や、要件を満たしているか微妙な点があると、労働局から電話や文書での「照会(質問)」が入ります。このやり取りにも時間がかかるため、遅延の一因となります。
ウワサの「ローカルルール」は存在するのか?
冒頭の例のように、神奈川では決定が出ているのに、東京や千葉ではまだ出ない…となると、「地域によって審査の厳しさやルールが違うのではないか?」と疑問に思われるかもしれません。
いわゆる「ローカルルール」についてですが、まず大前提として、厚生労働省が定める助成金の支給要領やマニュアルは全国共通です。特定の県だけが独自に要件を厳しくしたり、甘くしたりすることは原則としてありません。
では、なぜ実務上「地域差」を感じるのでしょうか。これは「ルールの違い」というよりも、「運用の差」や「審査状況の差」と捉えるべきです。
「差」が生まれる3つの要因
1.申請の集中度:
最低賃金が高い、あるいは引き上げ幅が大きい都市部(東京、神奈川、大阪など)や、中小企業の数が多い地域では、当然ながら申請が集中します。結果として、審査の待ち時間が長くなる傾向があります。
2.審査体制(マンパワー):
各労働局の助成金審査部門の体制(人員数)にも限りがあります。申請の集中度に対して人員が不足している場合、審査はどうしても遅れます。
3.審査の重点の置き方:
全国共通のルールとはいえ、最終的に判断するのは「人(審査官)」です。過去に不正受給が多かった地域などでは、特定のポイント(例:経費の妥当性、事業実態の確認など)をより慎重に(厳しく)見る傾向が生まれる可能性は否定できません。
したがって、「東京は審査が厳しい」というよりは、「東京は申請が集中しすぎていて、審査に時間がかかっている」というのが、現状の遅延の真相に近いと言えるでしょう。
交付決定を待つ間、申請者ができること
「では、ただ待つしかないのか?」と思われるかもしれませんが、申請者様ができることもあります。
1. 申請から2〜3ヶ月経過したら、進捗を確認する
申請から(不備の差し戻しなどを除いて)2ヶ月以上音沙汰がない場合は、申請先の労働局(または管轄のハローワーク)に、丁寧に進捗状況を問い合わせてみましょう。「審査が止まっていないか」を確認するだけでも、精神的な安心感が得られます。
(※ただし、審査を早めるよう催促するのではなく、あくまで「状況の確認」というスタンスが重要です。)
2. 照会や差し戻しには「最優先」で対応する
もし労働局から書類の不備や内容の確認(照会)で連絡が来た場合は、他の業務を一旦止めてでも、最優先で、かつ迅速・正確に対応してください。ここで対応が遅れると、審査の順番が後回しになり、さらに決定が遅れてしまいます。
3. これから申請する場合は「完璧な書類」を目指す
これから申請を控えている方、あるいは不備で差し戻しになった方は、「審査官が一読して理解できる、完璧な申請書類」を作成することが、結果として最速で交付決定を得る近道です。計画の具体性、見積書の整合性など、細部まで徹底的に確認しましょう。
まとめ:遅れていても審査は動いている
業務改善助成金の交付決定が遅れているのは、主に申請件数の急増によるもので、皆様の申請が放置されているわけではありません。多くの労働局で審査体制のキャパシティを超える申請が来ており、審査官も懸命に処理を進めている状況です。
大切なのは、不備のない申請を心がけ、もし照会があっても迅速に対応することです。ご不安な点や、ご自身の申請状況が特に心配な場合は、私たち社会保険労務士のような専門家にご相談いただくのも一つの手です。
設備投資と賃金引上げという、企業の未来に向けた前向きな取り組みです。無事に交付決定がおりることを心から願っております。
この記事の執筆者
社会保険労務士法人総合経営サービス肥後労務管理事務所
社会保険労務士 代表社員 白井 章稔
社会保険労務士法人 総合経営サービス 肥後労務管理事務所:https://sokei-sr.jp/
【王子オフィス】
〒114-0002
東京都北区王子2-12-10 総経ビル
【吉祥寺オフィス】
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-14 メディ・コープビル8 501号室
【信州松本オフィス】
〒390-0833
長野県松本市双葉 11-12