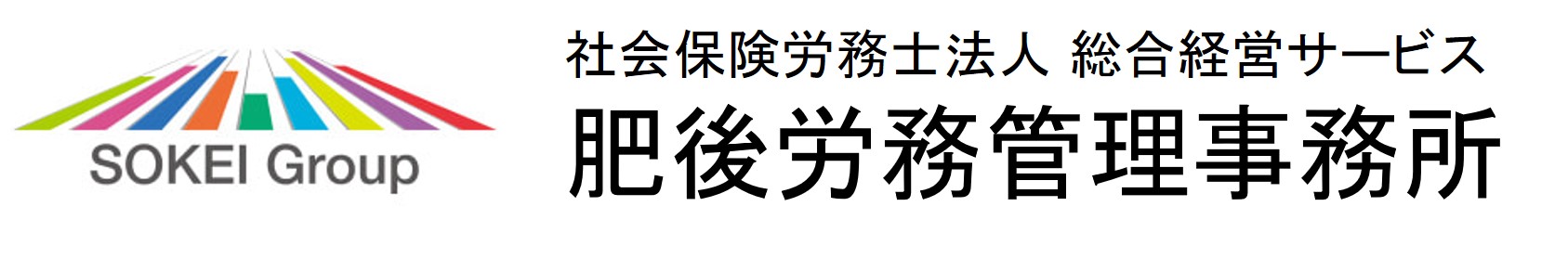育児中でも働きやすく!2025年度「柔軟な働き方選択制度等支援コース」を徹底解説
こんにちは。社会保険労務士の白井章稔です。企業の労務相談をお受けしていると、「育児中の優秀な従業員が、働き続けることが難しくなり離職してしまった」というお悩みを伺うことが少なくありません。いわゆる「3歳の壁」や「小1の壁」といった言葉に象徴されるように、育児と仕事の両立には多くのハードルが存在します。
特に中小企業にとって、一度育てた人材の離職は大きな痛手です。だからこそ、育児中の従業員が柔軟に働ける環境を整備し、人材を確保・定着させることが、企業の持続的な成長に不可欠です。
今回は、まさにそうした企業の取り組みを力強く後押しする「両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)」をご紹介します。この助成金は、仕事と育児の両立支援に取り組む事業主を応援するもので、中小企業のみが対象となっている点が大きな特徴です。
この助成金の「2つの柱」
このコースには、大きく分けて2つの支援内容があります。どちらか一方、あるいは両方に取り組むことで助成金が支給されます。
柱①:柔軟な働き方選択制度の導入・利用支援
育児を行う従業員のために、柔軟な働き方を可能にする制度を複数(3つ以上)導入し、実際にその制度を利用した従業員が出た場合に助成されます。
柱②:子の看護等休暇の「有給化」支援
法律で定められている基準を上回る内容の「子の看護等休暇」を、新たに有給で導入した場合に助成されます。
まずは、それぞれの支給額の概要を見てみましょう。
| 支援内容 | 支給額 | 備考 |
|---|---|---|
| 柔軟な働き方選択制度(3制度導入+利用) | 20万円(制度利用者1名あたり) | 1事業主あたり5人まで |
| 柔軟な働き方選択制度(4制度以上導入+利用) | 25万円(制度利用者1名あたり) | |
| 子の看護等休暇(有給化)支援 | 30万円 | 1事業主1回限り |
| 加算措置 | 制度利用延長加算(20万円) 情報公表加算(2万円) |
1事業主1回限り ※加算のみの受給は不可 |
※上記は厚生労働省「両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)支給申請の手引き(2025(令和7)年10月版)」に基づく概要です。
柱①:「柔軟な働き方選択制度」とは?
一つ目の柱は、従業員の多様なニーズに応えるための「制度の導入」と「利用」に対する支援です。
対象となる5つの制度
助成金の対象となるのは、以下の5つの制度群です。この中から3つ以上(4つ以上で支給額増額)を選んで導入する必要があります。
1.フレックスタイム制度/時差出勤制度
従業員の申出により、始業・終業時刻を調整できる制度です。時差出勤は、1日の所定労働時間を変えずに1時間以上繰り上げ・繰り下げることが要件です。
※フレックスタイムと時差出勤の両方を導入しても「1つの制度」としてカウントされます。
2.育児のためのテレワーク等
自宅やサテライトオフィスでの勤務を可能にする制度です。週または月の勤務日の半数以上利用できることや、時間単位での利用が可能であることなどが求められます。
3.柔軟な働き方を実現するための短時間勤務制度
法律で定められた「1日6時間」の短時間勤務だけでなく、例えば「1日7時間勤務」や「週休3日」など、柔軟な短時間勤務を選択できる制度です。
4.保育サービスの手配及び費用補助
ベビーシッターや一時預かりなど、臨時的な保育サービスの費用を事業主が補助する制度です。(恒常的な保育所費用などは対象外)
5.養育両立支援休暇制度
年次有給休暇や子の看護等休暇とは別に、新たに「有給」の休暇を設ける制度です。「1年度あたり10労働日以上」の付与、「時間単位」での取得、「中抜け(勤務時間の途中で取得)」が可能であることが要件です。
助成金受給の重要なポイント
これらの制度を導入する際、助成金を受給するためには以下の点が非常に重要です。
■ 就業規則への規定
導入する3つ(または4つ以上)の制度について、内容や利用手続きを就業規則または労働協約に明記する必要があります。
■ 対象者の範囲
導入する制度は、原則として「子が3歳以降、小学校就学前まで」の労働者が利用できるものとして設ける必要があります。
■ 「支援プラン」の策定
これが最大のポイントです。制度を利用したい従業員から申出があった場合、制度利用開始日の「前日」までに、上司または人事担当者が従業員と面談しなければなりません。そして、その面談結果に基づき、円滑な制度利用と利用後のキャリア形成を支援するための「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成する必要があります。
■ 利用実績
プランに基づき、従業員が制度利用を開始してから6か月間で、制度ごとに定められた基準(例:フレックスやテレワーク、短時間勤務は合計20日間以上、養育両立支援休暇は合計20時間以上など)を満たす利用実績が必要です。
柱②:「子の看護等休暇」の有給化支援
二つ目の柱は、子の看護等休暇の「有給化」です。
育児・介護休業法では、子の看護休暇(小学校就学前の子)の取得を認める義務はありますが、それを「有給」にする義務まではありません。そのため、多くの企業では無給扱いとなっています。
しかし、私が支援する企業様でも「子供が熱を出しても、給与が減ると思うと休みづらい」という従業員様の声は根強くあります。この助成金は、こうした法律の基準を上回る手厚い休暇制度の導入を支援するものです。
助成対象となる休暇制度の要件
助成対象となるには、以下の要件をすべて満たす休暇制度を、令和7年10月1日以降に新たに導入(就業規則に規定)する必要があります。
1.年次有給休暇とは別に付与される休暇であること。
2.有給であること(年休取得時と同等の賃金が支払われる)。
3.1年度あたり10労働日以上が付与されること。
4.時間単位(または時間未満単位)で取得できること。
5.始業時刻から連続、または終業時刻まで連続しない、いわゆる「中抜け」での取得が可能であること。
特に「時間単位」かつ「中抜け可」という要件がポイントです。「午前中に子供を病院に連れて行き、午後から出社する」といった無給の中抜け(私用外出)を認めている企業は多いですが、これを「有給の休暇」として制度化することが求められます。
これらの要件を満たす制度を導入すれば、30万円(1事業主1回限り)が支給されます。
申請前に必ず確認すべき共通要件
上記のいずれの支援を受ける場合でも、以下の共通要件を満たしている必要があります。
① 中小企業事業主であること。
② 雇用保険の適用事業主であること。
③ 法定の育児・介護休業制度の整備
そもそも、育児・介護休業法に基づく「育児休業制度」や「(3歳までの子を対象とした)短時間勤務制度」などが、法律の基準を満たした内容で就業規則にきちんと定められていること。
④ 一般事業主行動計画の策定・届出
「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画を策定し、管轄の労働局に届け出ていること。(※プラチナくるみん認定事業主を除く)
社労士から見た活用のポイントと注意点
この助成金を申請する上で、私たちが特に注意を払っている点をお伝えします。
1. 「プラン作成」は利用開始日までに!
柔軟な働き方選択制度の支援では、「面談の実施」と「支援プランの作成」を、必ず従業員の制度利用開始日の前日までに完了させなければなりません。利用開始日を過ぎてから慌てて書類を作成しても、助成金の対象外となってしまいます。日付の管理は徹底してください。
2. 就業規則の整備がすべての基本
助成金は「制度を導入」することが大前提です。導入するすべての制度(フレックス、テレワーク、有給休暇など)は、要件を満たす形で就業規則に明記する必要があります。「子の看護等休暇」の有給化についても、「時間単位」「中抜け可」といった文言が明確に規定されているかどうかが審査されます。
3. 客観的な利用実績の管理
6か月間の利用実績は、タイムカードや出勤簿、テレワークの場合は業務日報などで客観的に確認できる必要があります。「保育サービス費用補助」であれば領収書や補助額の支払い実績など、証拠書類を確実に保管・管理する体制を整えておくことが重要です。
まとめ
育児中の従業員が能力を発揮し続けられる環境を整備することは、もはや福利厚生ではなく、企業の「人材戦略」そのものです。「両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)」は、その戦略を金銭面でサポートする強力なツールです。
ただし、活用にあたっては、複数の制度設計、就業規則の改定、詳細なプラン作成、利用実績の管理など、専門的な対応が求められます。制度導入から申請まで、ぜひお近くの社会保険労務士にご相談ください。
執筆者:社会保険労務士法人総合経営サービス肥後労務管理事務所
社会保険労務士 代表社員 白井 章稔
社会保険労務士法人 総合経営サービス 肥後労務管理事務所:https://sokei-sr.jp/
【王子オフィス】
〒114-0002
東京都北区王子2-12-10 総経ビル
【吉祥寺オフィス】
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-14 メディ・コープビル8 501号室
【信州松本オフィス】
〒390-0833
長野県松本市双葉 11-12