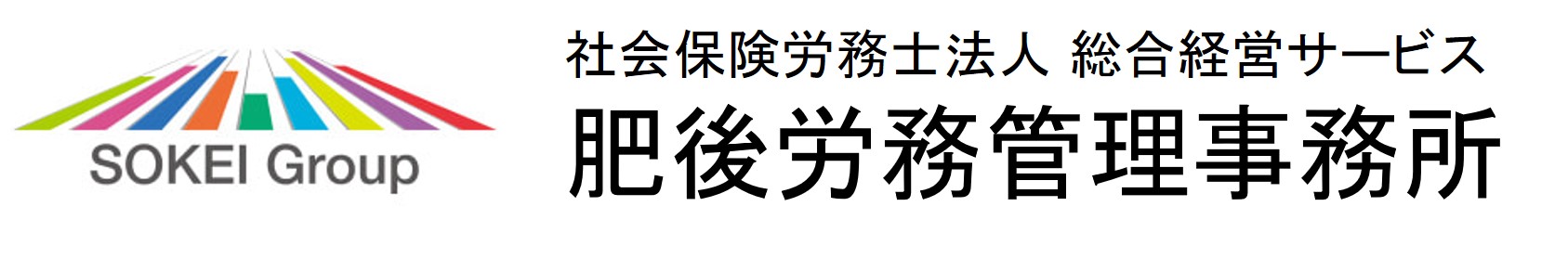「退職代行を使って退職する社員」が出たとき、会社はどう対応すべき?
2025/05/21
近年、「退職代行」という言葉をよく耳にするようになりました。
特に毎年4月から5月にかけて、新入社員や若手社員を中心に「退職代行サービス」を利用して突然辞めてしまうケースが増えています。
人事担当者や経営者の方からすると、
「退職代行会社から連絡が来て驚いた」
「社員本人とは一切連絡がつかないが、どう対応すればよいのか?」
など戸惑いを感じてしまう場面が増えているのではないでしょうか。
今回は、社員が退職代行を利用した場合の法的な対応や会社として行うべき具体的な実務対応、そして二次トラブルを防ぐための社内ケアについて解説します。
そもそも「退職代行」とは?
退職代行とは、社員本人に代わって退職の意思を会社に伝えるサービスのことです。
利用者本人は「退職を切り出しにくい」「上司や同僚に会いたくない」などの心理的な理由で、このサービスを利用します。
サービス提供者には弁護士が行うものと民間企業が行うものがありますが、弁護士でない場合は交渉行為が許されていません。そのため会社としては「退職を伝える」以上の交渉や議論を退職代行業者と行う必要はありません。
経営者がよく抱く疑問—「就業規則に『退職は1ヶ月前の届け出』と書いてあるのに・・・?」
退職代行業者から連絡があった際、多くの経営者や人事担当者が最初に感じる疑問があります。
それは、「当社の就業規則では退職する場合は1ヶ月前、場合によっては3ヶ月前に申し出ることが定めてあるのに、なぜ退職代行サービスを利用すると短期間で辞められるのか?」という点です。
確かに、多くの企業の就業規則には「退職は原則として1ヶ月前までに届け出ること」などの記載があります。しかし実は、この就業規則の記載よりも法的に優先されるのが、民法の規定なのです。
具体的には、民法第627条には以下の規定があります。
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」
つまり、会社の就業規則で「退職の申し出は1ヶ月前」「3ヶ月前」と定めてあっても、この民法の規定が法律上は優先されます。そのため、退職代行業者が示した退職日がこの規定を満たすものであれば、法的にはその日を退職日として認めざるを得ないのです。
退職代行を使われたときの会社の法的対応とポイント
実務的には、退職代行を利用した社員に対して会社側が強く抵抗するのは難しいのが現状です。
社員本人の退職意思が確認できれば、それ以上の交渉や議論は原則行いません。感情的な対応をするとトラブルを悪化させるリスクがあります。
実務上、会社が行うべき具体的な対応とは?
退職代行を通じて社員の退職意思が伝えられた場合、会社としては感情的にならず、法的に適切な実務対応を淡々と進めることが求められます。以下が、対応すべき主な内容です。
まずは、雇用保険・社会保険の資格喪失手続きを行います。退職日が確定した時点で、雇用保険被保険者資格喪失届や、健康保険・厚生年金保険の資格喪失届を提出しなければなりません。
次に、源泉徴収票を発行し、退職者本人へ郵送します。退職後に転職する際に必要になるため、スムーズな手続きを心がけましょう。
また、退職証明書については、本人や退職代行業者から請求があれば作成・交付が必要です。証明内容は事実に基づき適切に作成しましょう。
あわせて忘れてはならないのが、住民税の異動届出です。退職後の住民税は会社を通じての「特別徴収」から、本人が支払う「普通徴収」に切り替わります。そのため、各市区町村に対して「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。提出漏れがあると、退職者に納付書が届かず、結果として住民税の延滞やトラブルに発展する恐れがあります。
さらに、健康保険証などの公的書類だけでなく、社用のパソコンや携帯電話、セキュリティカード、制服などの貸与品も返却対象となります。返却が完了したかどうかを確認・記録し、トラブルの防止に努めましょう。
これらの手続きを、感情を交えず、事実と法律に基づいて確実に進めることが、労務リスク回避につながります。
二次被害を防ぐために—退職代行の「連鎖」を防ぐポイント
退職代行を利用する社員が出ると、「他の社員にも同じような不満や退職願望があるのではないか」と不安に感じる経営者や人事担当者は少なくありません。こうした場面で最も注意すべきなのは、退職代行を利用した社員に対して感情的な反応を見せたり、ネガティブな発言を社内で共有してしまうことです。
職場の空気が悪くなると、残っている社員のモチベーションにも悪影響が及び、さらなる退職の連鎖を招きかねません。だからこそ、会社としては“去った人より残る人”への対応に意識を向けることが重要です。
たとえば、次のような取り組みが効果的です。
・日頃から社員との対話の機会をつくり、コミュニケーションを密にする
・小さな悩みや不満も相談しやすい職場づくりを心がける
・メンタルヘルス対策や定期的なキャリア面談の仕組みを取り入れる
こうしたケアを積み重ねることで、社員の不安を軽減し、「ここで働き続けよう」と思える職場環境を築くことができます。結果として、退職代行の再発リスクを下げる最も有効な対策となります。

「感情的な対応」は最も避けるべき
突然の退職代行利用に戸惑い、社員本人と連絡がつかないことに腹が立つのは当然の感情です。しかし、ここで感情的に行動すると、さらに状況が悪化し、職場のモラル低下を招きます。
会社としては、「退職代行を利用すること自体を防げなかったこと」を反省材料として、冷静に組織改善を考える方向に気持ちを切り替えるのが適切です。そうすることで、残った社員に対しても前向きな職場環境を提供できます。
まとめ—冷静かつ法的に正しい対応が重要
退職代行を使った退職に会社として強く抵抗することは、現実的には難しいのが実情です。むしろ、法的に適切な実務対応を速やかに進めることと、感情的な対応を避けて職場環境のケアを徹底することが重要です。
退職代行のような労務トラブルは、組織として適切な対応方法を確立しておけば、大きな問題になる前に未然に防ぐことが可能です。自社での具体的な対応方法や労務トラブル全般について不安をお持ちの場合は、ぜひ当社、総合経営サービスへお気軽にご相談ください。
社会保険労務士法人 総合経営サービス 肥後労務管理事務所:https://sokei-sr.jp/
【王子オフィス】
〒114-0002
東京都北区王子2-12-10 総経ビル
【吉祥寺オフィス】
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-14 メディ・コープビル8 501号室
【信州松本オフィス】
〒390-0833
長野県松本市双葉 11-12