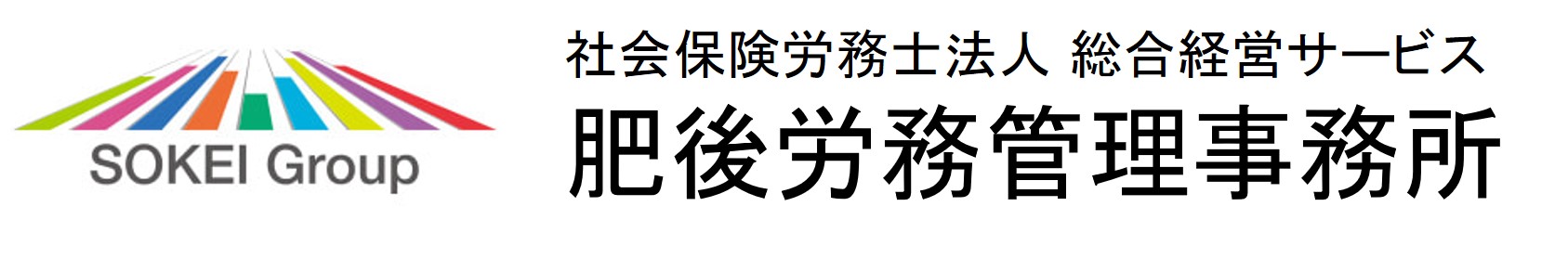従業員100~300人規模の企業様必見:給与計算を外注すべきタイミングとコスト比較シミュレーション
給与計算BPOの市場動向と背景
近年、中堅企業を中心に給与計算アウトソーシング(BPO)のニーズが高まっています。
実際、国内の人事・総務関連業務アウトソーシング市場は2022年度に前年度比7.0%増と大きく成長し、2023年度も6.7%増の拡大が予測されています。
背景には慢性的な人手不足により「間接業務を外部委託して社員をコア業務に集中させたい」という企業ニーズの高まりがあり、DX推進やテレワーク普及も後押しして間接業務アウトソーシングの流れが加速しています。
特に給与計算のように専門知識を要する業務では、自社で抱え込まず外部の専門家に任せるメリットが注目されています。実際、ある調査ではビジネスリーダーの75%が給与計算プロセスの大部分または全体の外注に前向きと報告されており、2023~2024年にかけて給与計算BPOの需要はさらに高まっていると言えるでしょう。
従業員100~300人企業における給与業務の課題
では、社員数100~300名規模の中堅企業が直面しがちな給与計算業務の課題とはどのようなものでしょうか。以下に主な課題とその業務・経営への影響を解説します。
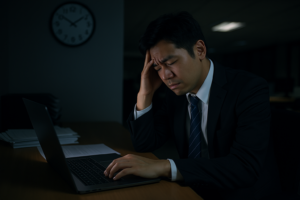
法改正対応の負荷とミスのリスク
ここ数年、給与計算に関わる法改正が相次いでおり、社内での対応が大きな負担となっています。
例えば2023年4月から中小企業でも「月60時間超の残業に対する割増賃金率50%以上」が義務化されました。こうした法改正に追随できず対応が遅れると、残業代の未払いといった法令違反リスクや従業員の信頼低下につながりかねません。
また、税制改正や社会保険料率の変更のたびに給与計算ソフトの設定更新や担当者の知識習得が必要となり、その都度多くの時間とコストを費やすことになります。事実、2023年・2024年の改正内容は賃金や労働時間に直結するためミスが許されず、対応漏れが致命的な問題になり得ると指摘されています。法改正対応に追われ本来業務に手が回らない状況は、企業にとって大きなリスクと言えるでしょう。
担当者の残業過多と業務負荷の増大
従業員数が増えるほど、毎月の給与計算・勤怠集計にかかる工数も膨れ上がり、人事担当者の負担は無視できないものになります。
特に支給日直前は確認作業や修正対応が集中し、担当者の恒常的な残業が発生しているケースも少なくありません。業務過多による担当者の疲弊はヒューマンエラーの誘因にもなります。万が一計算ミスで給与の過不足支給が起これば、追加支給や差額回収など余計な手間とコストが発生し、従業員の士気にも影響を与えてしまいます。
また、このような負担の大きい状態が続くと担当者の離職リスクも高まり、人材確保が難しい昨今では新たな採用コスト増につながる恐れもあります。
中堅企業では人事部門の人員に限りがあるため、一人ひとりの担当業務が肥大化しやすく、結果として残業代など間接コストの増大や労務トラブルの火種となってしまうのです。
業務の属人化による継続性リスク
給与計算業務は社内でも限られた担当者だけがノウハウを把握している場合が多く、業務の属人化が進みがちです。給与データは機密情報で扱える人が限られることや、企業ごとに計算ルールや手当体系が異なり標準化しにくいことが原因です。
その結果、担当者が急病や退職で不在になった際には業務が滞るリスクがあります。実際、「担当者が急に不在となった時に、別の社員が過去資料を手探りで見ながら給与計算を間に合わせるのは非常に大変だ」との指摘もあります。
属人化した状態では引き継ぎも容易ではなく、最悪の場合給料日の支給遅延や計算ミス発生にもつながりかねません。中堅企業にとって、特定の個人に業務が依存する状況はビジネスの継続性を脅かすリスク要因となります。
以上のような課題により、法令順守や業務品質の確保、人件費管理の面で中堅企業の給与計算業務は大きな悩みを抱えがちです。
こうした状況を踏まえ、次に内製(自社処理)と外注のコスト比較を具体的な数字で見てみましょう。
内製 vs 外注:中堅企業のコスト比較シミュレーション
給与計算業務を「内製で行う場合」と「専門業者へ外注する場合」で、年間コストにどの程度の差が出るのかをモデルケースで比較してみます。
大企業のように十分な人員を割けない中堅企業では、内製コストの割高感が相対的に高くなる傾向があります。ここでは従業員150名規模の会社を想定し、両者の年間コストを試算します。
〈モデルケース:従業員150名の場合〉
【内製(自社処理)の場合のコスト】
給与計算を担当する人事担当者1名を専任で配置すると仮定します。その人件費(給与・賞与・社会保険負担分)は年間約500万円程度と見積もります。
加えて給与計算ソフトのライセンス料や法改正に対応する研修費用などに年間約50万円を要すると仮定すると、内製によるコスト総額は年間約550万円となります。
【外注(給与計算BPO)の場合のコスト】
アウトソーシング費用は一般的に「従業員1名あたり月額約1,500円前後」が相場です。
このケースでは150名分で月額約22.5万円、年間では約270万円の計算になります。(社会保険手続を含む。年末調整や賞与計算は別途。)。初年度は別途初期設定費用が発生する場合もありますが、それを考慮しても年間300~350万円程度に収まるケースがほとんどです。
試算の結果、外注を利用すれば年間コストは内製の約1/2程度に削減できる見込みです。仮に従業員規模が増えて200名・300名となれば、内製では追加で人件費が発生する可能性が高くコスト差はさらに拡大するでしょう。
一方、外注コストは人員増加に比例する従量課金制であっても1名あたり単価は低減傾向にあるため、規模が大きくなるほど外注のコスト優位性は高まると考えられます。
もちろん業務内容や社内体制によって実際のコストは変動しますが、中堅規模においてはアウトソーシングの方が費用対効果で優れるケースが多いと言えるでしょう。
次に、具体的にどのようなタイミングで給与計算の外注を検討すべきか、判断の目安となるポイントを整理します。
給与計算を外注すべきタイミング【チェックリスト】
以下のような状況に心当たりがあれば、給与計算業務の外注化(BPO導入)を検討すべきタイミングかもしれません。
☑法改正対応に追われている:残業代計算や税額計算など、最近の法改正への対応に社内対応が追いつかず不安がある。
☑給与計算担当者の残業が慢性化:毎月の給与処理期間中に担当者が深夜残業や休日出勤をしており、担当者の負担が限界に達している。
☑給与計算ミスや支給遅延が発生した:計算誤りによる追加支給・控除や、締め処理の遅れによる給与の遅配などトラブルが起きたことがある。
☑業務が特定の担当者に属人化している:給与計算のノウハウが一人の社員に集中しており、その人が不在になると業務が回らない恐れがある。
☑社員数の増加で処理が追いつかない:従業員100名を超え業務量が膨らみ、現状の人員・体制ではミスなく回すのが難しくなってきた。
☑人件費・効率面で限界を感じている:専門人員の増員やシステム投資を検討しているがコストが重く、現状の内製運用に改善の余地を感じている。
上記のチェック項目に当てはまる場合、まさに「給与計算を外注すべきタイミング」と言えます。アウトソーシングの検討は早めに行い、万全の体制で給与業務を進められるようにしましょう。
当社サービスの特徴:事前ヒアリングから改善提案まで他社にない手厚いサポート
給与計算業務の外注を検討する際は、サービス提供企業のサポート内容にも注目することが重要です。
当社の給与計算BPOサービスは、単なる計算代行に留まらない包括的な支援を行い、一般的なBPOサービスとは一線を画しています。以下に当社サービスの主な特徴と強みをご紹介します。
☑事前ヒアリングで現状を徹底分析
導入前に専門スタッフが貴社の給与体系・勤怠ルールや現在の業務フローを詳しくヒアリングし、課題を洗い出します。
現行業務のどこに非効率やミスのリスクがあるかを可視化し、委託後の運用に最適なプロセスを設計します。これにより「ただ外注する」だけでなく、現状業務そのものの改善ポイントが明確になります。
☑法令遵守を確認する万全の体制
最新の労働関連法や税制改正に精通した社労士・スタッフが、貴社の給与計算が法令に適合しているか事前にチェックします。
就業規則や給与規程が最新の法改正に対応しているかを確認し、不備があれば是正の提案を行います。こうしたコンプライアンス確認により、アウトソーシング後も法改正への対応漏れを防止し、安心して業務を任せていただけます。
☑給与体系・勤怠管理の改善提案
当社では単に渡されたデータを処理するだけでなく、より良い給与計算体制の構築にも踏み込んで支援します。綿密なヒアリングと業務調査を通じて現行フローを分析し、必要なタスクを整理・標準化することで属人化しがちな業務の改善を図ります。
例えば、煩雑な手当計算ルールの簡素化や勤怠管理方法の見直しなど、業務効率化につながる具体策を提案します。他社の一般的なBPOサービスが「決められた手順で計算する」受動的な姿勢に留まる中、当社は課題解決まで見据えた能動的なサポートを提供します。
これら以外にも、導入時のきめ細かなフォローやセキュリティ万全のデータ管理体制など、当社ならではの強みがあります。単純な外注ではなく「パートナー」として貴社の人事労務を支えるサービスであることが、当社給与計算BPOの最大の特徴です。
導入事例:給与計算アウトソーシングで課題解決した中堅企業
最後に、給与計算BPOの導入によって課題を解決した中堅企業の事例を3社ご紹介します。

事例1:法改正対応の負担を解消した製造業A社(群馬県 従業員120名)
製造業のA社では、ここ数年の度重なる社会保険・税務関連の法改正対応に苦慮していました。
従業員120名分の給与計算を人事担当者1名で担っていたため、毎年のように変わる計算ルールのチェックやシステム修正に追われ、本来の労務管理業務に支障が出ていたのです。
そこで当社の給与計算アウトソーシングをご利用いただいたところ、専門スタッフが法改正事項を確実に反映した計算フローを構築。年末調整や住民税納付など煩雑な業務もすべて委託し、担当者はチェックと他の人事業務に専念できるようになりました。
その結果、ミス発生リスクが解消され、人事労務担当者の心理的・時間的負担も大幅に軽減されました。今では安心して本業に取り組んでいただいています。
事例2:残業ゼロで人事負荷軽減に成功したIT企業B社(東京都 従業員250名)
IT業のB社は急成長に伴い従業員が増加し、給与計算担当者2名が毎月支給日前1週間は深夜まで残業する状況になっていました。
特に多様な勤務形態の社員が多く、残業代計算や深夜手当の確認に時間がかかっていたためです。担当チームは過労気味でミスも散見されるようになり、新たに人員を増やすか悩んだ末に当社へご相談がありました。
当社サービス導入後は、月次給与計算から各種手当・控除の計算、さらには年末調整までフルアウトソーシング。クラウド勤怠システムとも連携しデータ取り込みを自動化したことで、担当者の手作業を大幅削減しました。
結果として給与計算業務にかかっていた残業はほぼゼロとなり、人事部門は空いた時間を採用や社員研修など戦略業務に充てることが可能になりました。
B社では「アウトソーシングでこれほど業務効率が上がるとは思わなかった」と大きな効果を実感いただいています。
コスト面でも、仮に人員を1名増やす場合と比べて約30%以上の削減となり、経営層にも高く評価されています。
事例3:担当者退職によるリスクを回避した小売業C社(愛知県 従業員300名)
全国に店舗を持つ小売業C社では、長年給与計算を担当してきたベテラン社員の退職が決まり、業務継続性の危機に直面しました。
給与計算はそのベテラン社員にほぼ任せきりで、他のスタッフは細部を把握しておらず、引き継ぎにも不安がある状態でした。
そこで退職に合わせて当社のアウトソーシングサービスを導入。導入時に当社スタッフが給与計算フローを一から棚卸ししてマニュアル化し、複雑な計算ルールもシステム上に再現しました。結果、ベテラン社員の退職後も給与計算業務は滞りなく遂行され、属人化していた業務の標準化と可視化に成功しました。
C社では「もう特定の社員に頼らずとも給与計算が回る」と安心いただくとともに、人事部門の体制見直しにも着手する余裕が生まれました。
このように、人に依存していた重要業務をアウトソーシングすることで事業継続性と内部統制の強化につながった好例です。
以上のように、中堅企業における給与計算BPO導入は法令対応の強化、人件費・業務負荷の削減、リスク分散による安心感など多方面に効果を発揮します。
自社の状況と照らし合わせ、少しでも課題を感じているようであれば、ぜひ専門サービスへのアウトソーシングを検討してみてください。
まずは無料コストシミュレーション&ご相談を!
本記事をご覧になり「自社でも給与計算の外注を検討したい」と感じられた方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。
御社の従業員規模や現在の業務状況を入力いただくだけで、外注化した場合のコスト試算と削減効果を把握できます。また、具体的なお悩みやご質問がございましたら、いつでもお問い合わせフォームよりお問い合わせいただけます。専門スタッフが貴社の状況に合わせて最適なプランと解決策をご提案いたします。
給与計算の外注化は、人事労務のリスクと負荷を軽減し、コア業務に集中できる環境を整える有効な手段です。
この機会にぜひ一度、社内の給与計算プロセスを見直し、プロの力を借りる選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。貴社からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
社会保険労務士法人 総合経営サービス 肥後労務管理事務所:https://sokei-sr.jp/
【王子オフィス】
〒114-0002
東京都北区王子2-12-10 総経ビル
【吉祥寺オフィス】
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-14 メディ・コープビル8 501号室
【信州松本オフィス】
〒390-0833
長野県松本市双葉 11-12