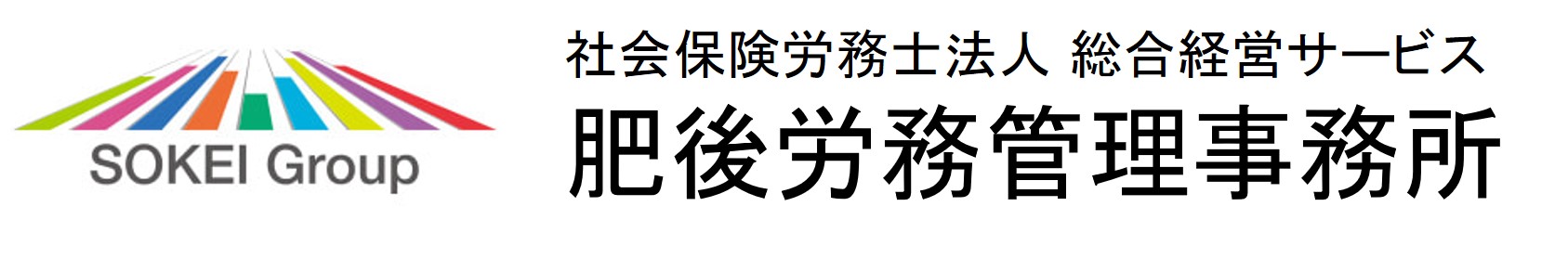【実例】助成金申請で「まさか」の事態!交付決定後に申請対象が売り切れ?!
こんにちは。社会保険労務士法人総合経営サービス 肥後労務管理事務所の白井です。
私たちは、企業経営に役立つ様々な助成金の申請サポートを日々行っています。助成金の申請は、計画段階から支給決定まで、多くの手続きと時間を要します。順調に進むのが一番ですが、時には「想定外」の事態が発生することも少なくありません。
本日は、私たちが実際に経験した、非常に稀な「交付決定後の増額変更」が認められた事例についてご紹介します。労働局の柔軟な対応に助けられたこのケースは、助成金申請の難しさと、同時に可能性も示しています。
事例概要:福祉車両導入のための助成金申請
ご相談いただいたのは、県内でリハビリテーション施設などを運営されている法人様でした。施設を利用される患者様(利用者様)の送迎サービスを拡充・効率化するため、新たに福祉車両(車いすリフト付き車両)の導入を計画されていました。
私たちは、事業場内最低賃金の引き上げと生産性向上のための設備投資を支援する「業務改善助成金」の活用をご提案しました。折からの物価高騰等の影響も受けておられたため、「特例事業者」としての枠組みで申請をサポートすることになりました。この制度では、生産性向上に資する設備(今回は患者様の送迎用車両)の導入費用の一部が助成されます。
事業者様は、コストを抑えるために「中古」の福祉車両を選定。状態の良い車両を見つけ、その見積書を添付して労働局に申請書類を提出しました。
審査は順調に進み、無事に申請内容が認められ、「交付決定」の通知が届きました。
最大のピンチ:交付決定された中古車が「売り切れ」
交付決定の連絡を受け、事業者様がすぐにその中古車販売店に連絡を入れたところ、衝撃の事実が告げられます。
「申し訳ありません、あの中古車はタッチの差で売れてしまいました…」
中古車は一点物です。申請から交付決定までには一定の期間がかかります。その間に、他の方が購入してしまうリスクは常にあるのです。
事業者様も私たちも、頭が真っ白になりました。助成金は「交付決定された特定の車両」に対して認められたものです。その車両が手に入らないとなれば、計画そのものが頓挫しかねません。
立ちはだかる「助成金の原則」
慌てて、事業者様は別の福祉車両を探しました。幸い、同等スペックの別の中古車を見つけることができましたが、ここで新たな問題が発生します。
新しい車両の見積額が、当初交付決定された金額よりも高額だったのです。
助成金の原則:交付決定額の増額は「不可」
助成金制度における「交付決定」とは、「申請された計画と見積額に基づき、その金額を上限として助成します」という行政との約束です。
● 計画より安く実施できた場合:実際に支払った安い方の金額に基づき、助成額も減額されます。
● 計画より高額になった場合:原則として、交付決定額を超える部分は助成されません。差額はすべて自己負担となります。
これが大原則です。申請者側の都合で「もっと高いものに変えたい」といった理由での増額変更は、まず認められません。
今回のケースをこの原則に当てはめると、新しい高い車両を購入しても、助成されるのは「当初の安い方の金額」まで。差額の自己負担が大きくなり、事業者様の負担が大幅に増えてしまいます。
逆転の交渉:労働局担当官の「特別な配慮」
私たちは、この状況を打開すべく、すぐに労働局の審査担当官に連絡を取りました。
私たちが伝えたこと
まず、事実関係をありのままに説明しました。
1.交付決定を受けた車両が「中古車」であったこと。
2.交付決定の連絡を受け、すぐに発注しようとしたが、タッチの差で売れてしまっていたこと。
3.事業者側に故意や過失はなく、中古車市場の特性上、不可抗力であった側面が強いこと。
4.代替車両を探したが、当初の金額内で同等品を見つけることができず、やむを得ず高額な見積もりとなったこと。
5.当初の計画の趣旨(患者様の送迎サービス向上のための福祉車両導入)に変更はないこと。
その上で、新しい車両の見積書を提出し、「新しい見積額で交付決定額を変更(増額)していただくことはできないか」と、誠心誠意、事情を説明し相談しました。
労働局の柔軟な判断
担当官の方も、当初は「原則として増額変更は難しい」という姿勢でした。これは当然の反応です。
しかし、私たちが粘り強く状況を説明し、特に「対象が中古車であり、申請から決定までのタイムラグの間に売れてしまった」という特殊事情を訴えた結果、担当官の方が上席にも相談してくださいました。
そして、最終的に「今回は、中古車という特殊な事情をやむを得ない理由として考慮し、例外的に、新しい高い方の見積額に基づく交付決定額への変更を認めます」という、非常にありがたい回答をいただくことができたのです。
この稀な事例から学べること
今回の労働局の柔軟なご判断には、本当に感謝しかありません。この事例は、助成金申請において非常に重要な教訓を私たちに示してくれました。
1. 「原則ダメ」でも諦めない
助成金には厳格なルールがあります。しかし、行政も「鬼」ではありません。ルールブック通りにいかない「やむを得ない事情」が発生した場合、その理由を論理的かつ誠実に説明することで、例外的な対応(裁量)が認められる可能性はゼロではありません。
2. 中古品を対象とするリスク管理
中古品を助成対象とする場合、今回のような「売り切れリスク」が常につきまといます。可能であれば、申請前に販売店に事情を話し、交付決定まで仮押さえできないか相談するなどの対策も有効かもしれません(ただし、助成金によっては「交付決定前の発注・契約」自体がNGとなるため、細心の注意が必要です)。
3. 専門家(社労士)の交渉力
このようなイレギュラーな事態が発生した際、行政側と冷静に交渉し、事情を的確に説明できるのが専門家の強みです。私たちは、ルールの原則を熟知しているからこそ、「どこが例外にあたるのか」を整理し、担当官に理解を求める交渉ができます。
まとめ:助成金申請は「人」対「人」
助成金申請は書類との戦いのように思われがちですが、最終的には「人(申請者・社労士)」と「人(行政の担当官)」のやり取りです。
計画通りに進まないトラブルが発生した時こそ、専門家にご相談ください。ルールに則りつつも、事業者の皆様の状況に寄り添った最善の解決策を、私たちも一緒に探していきます。
業務改善助成金をはじめ、助成金の活用でお困りのことがあれば、ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。
執筆者
社会保険労務士法人総合経営サービス肥後労務管理事務所
社会保険労務士 代表社員 白井 章稔
社会保険労務士法人 総合経営サービス 肥後労務管理事務所:https://sokei-sr.jp/
【王子オフィス】
〒114-0002
東京都北区王子2-12-10 総経ビル
【吉祥寺オフィス】
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-14 メディ・コープビル8 501号室
【信州松本オフィス】
〒390-0833
長野県松本市双葉 11-12